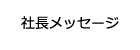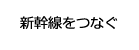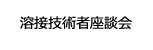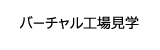先輩の声
峰製作所で働く社員のキャリアや仕事に対する想いをご紹介します。

業務内容
私は現在、日次から月次まで幅広い経理業務を担当しております。
日次業務では、小口現金の管理や銀行口座の入出金確認、売掛金の消込作業など、基礎的な処理を正確かつ効率的に行うことを心がけています。
月次業務では、取引先からの請求書確認、社内の支払申請、振込データの作成などを担当し、スケジュールに沿った正確な支払管理を行っています。海外取引先への支払に関しては、英語の請求書を確認し、振込依頼書を作成して銀行の担当者とやり取りするなど、海外送金にも対応しています。
また、取締役会資料の作成なども担当しています。売上の推移、前月比や前年同月比の分析などを表にまとめ、経営層が意思決定に活用できるよう、見やすさと正確さにこだわって作成しています。
日々の業務を通じて、経理としての基本的なスキルに加え、取引先や銀行担当者とのやり取りを通じたコミュニケーション力や、社内との調整力も身につけてきました。今後は、より広い視点で会社全体の数字を捉えるような業務にも挑戦していきたいと考えています。
業務のおもしろさ・魅力、印象に残っている業務など
経理の仕事の面白さは、日々の数字を通して会社全体の動きが見えてくるところにあると感じています。日次の現金出納や費用の計上、月次の支払管理や業績集計といった一つひとつの業務が、最終的に会社の意思決定につながっているという実感があります。
特に毎月の業績資料をまとめる際には、売上や費用の動きに「なぜそうなったのか」という背景を読み取ることで、数字の裏にある現場の動きや経営の意図を考える癖がつきました。単なる集計作業ではなく、数字が変化した要因を理解しようとすることで、資料の質も大きく変わると感じています。
一方で、数字を扱う仕事だからこそ、小さなミスが大きな影響を与えるというプレッシャーもあります。実際にミスをしてしまったこともありましたが、そこで終わらせず、なぜミスが起きたのか、どうすれば再発を防げるかを考え、業務に組み込める仕組みづくりを行うようにしています。
『峰』だからできること
当社では、仕訳入力や売掛金管理から支払業務、資料作成まで幅広く経験でき、業務全体を見渡せるのが魅力です。経営層や他部署との距離も近いため、数字の背景にある実態をつかみやすく、会社の意思決定に貢献している実感を持てます。また、自ら業務フローを改善できる余地が大きく、関数やチェックリストを用いてミス防止に取り組むなど、自分の工夫がそのまま成果につながる点にやりがいを感じています。
経理部は4人と少ない人数ですが誰かが休んだ時はカバーし合ったりと、協力的な社風があることも大きな魅力です。

今後の目標
業務面では、年次処理を少しずつ習得しながら、将来的には税務など、より専門性の高い分野にも取り組んでいきたいと考えています。また、経営企画部と連携し、戦略的な視点から数字を捉えられる力を養いたいと思っています。
プライベートでも簿記やIT系の資格取得目標に知識の幅を広げて業務の効率化を行っていきたいです。
学生へのメッセージ
仕事を通じて、やりたいことをぜひ見つけてください。それが入社前でも入社後でも構いません。企業選びで本当に大切なのは、「知名度」ではなく、「自分が成長できる環境か」「何を成し遂げたいのか」という視点だと私は思います。仕事は単に業務をこなすだけでなく、自己実現の場でもあります。入社後はぜひ、自分の強みを理解し、目標を明確にしたうえで、理想とするキャリアを築いていってください。
1日のスケジュール
出社
9:00
始業
メールチェック
各支店からの問い合わせ対応などを行います。イレギュラーがあれば、支店の担当者と電話でやりとりしたりすることも。
10:00
外出
銀行に伺い、海外取引先向けの送金資料を提出します。外に出ることでリフレッシュにもつながります。
11:45
昼食
13:00
経費精算
旅費を中心にその他経費精算を行います。税区分や税率に注意しつつ会計ソフトへ入力します。
14:00
資料作成
取締役会や支払関連資料を作成します。会社の意思決定に関わる重要な資料なので完成後は上司と相互確認を必ず行います。
16:00
入出金確認
現金出納を行った分や金融機関からの入金案内を確認・処理します。金額に相違が無いかを入念にチェックし差異が無いことを確認します。
17:45
終業
お疲れ様でした。月末/月初は残業することもあります。
学生時代のエピソード、趣味、休日の過ごし方など
休日は趣味の釣りによく出かけます。長期休暇が取れるときには、伊豆大島や神津島など、船で数時間かかる離島まで足を延ばすこともあります。目標としていた魚を釣り上げた瞬間の達成感は、何度味わってもたまりません!
また、釣るだけでなく持ち帰って料理するのも楽しみのひとつです。実家が飲食店ということもあり、子どもの頃から包丁を握っていたので、料理にはちょっとした自信があります(笑)。なにより、自分が振る舞った料理を「おいしい」と言って食べてくれる家族の笑顔を見ると、とても嬉しくなります。
(写真は神津島で釣りをしているところです。)

先輩の声 用語集
1.車上転換装置 ^
広大な製鉄所などの構内鉄道で、列車の運転手が運転手席から容易に進行方向を切り換えられるように工夫された転換装置。
2.転てつ機 ^
分岐器を動かし、線路を変えて列車の進行方向を切り換えるもの。当社の製品は全国の製鉄所構内を中心にご使用いただいている。
3.無人信号所制御装置 ^
列車の運転手が無線で信号所に送った信号により、自動で列車の進行ルートをセットする装置。
4.列車集中制御装置 ^
列車の運転手が無線で信号所に送った信号を元に、手動で列車の進行ルートをセットする装置。
5.誘導無線設備 ^
列車の運転手が進行ルートを信号所に無線で送信する装置。
6.車両秤量機(ひょうりょうき) ^
貨車に積載した荷物の重量を測るもの。
7.信号保安装置 ^
列車の位置やポイントの向き等を検知し、その状態を表示したり切り換える装置。
8.大型NC機械 ^
数値により制御された工作機械。プログラムにより加工の位置、方向、速度を制御する。
9.鉄道用分岐器、分岐器 ^
一つの線路から二つ以上の線路に分岐させる装置。これを動かすには転てつ機が必要。
10.トングレール ^
分岐器の先端に位置し、列車の進行方向を振り分ける部分。転てつ機はこの部分に取り付けられる。
11.クロッシング ^
分岐器の一部で、レールがクロスしている箇所。分岐した線路のどちらにも列車が進めるようになっている。
12.ガードレール ^
分岐器の一部で、クロッシングを通過する列車が脱線しないために敷設するもの。
13.ゴールドサミット溶接 ^
当社が1979年にドイツのエレクトロ・テルミット社と技術提携し、テルミット溶接工法(酸化金属とアルミニウム間の脱酸反応を溶接に応用したもの)を日本の鉄道へ適合できるようにしたレール溶接方法。従来のものより機動性に優れ、短時間で施工が出来る。在来線を中心に幅広く用いられ、現地で行うJR各社のレール溶接施工の約40%を占めている。
14.ガス圧接 ^
レール溶接方法の一つであり、レール接合部をガス炎で加熱して圧力を加えながら、レールを溶かすことなく接合する方法。
15.エンクローズアーク溶接 ^
レール溶接方法の一つであり、レールの形状に合わせて周囲を銅ブロックで囲み、溶接棒に電流を流し、放電の熱で溶接棒を溶かし、溶接する方法。
16.非破壊検査 ^
対象物を破壊することなく、キズの状況を調べる検査。目視や放射線や超音波、磁気などを使用してキズを調べる。
17.残留応力測定試験 ^
対象物に外から作用していた力が全て取り除かれた後に物体内部に残存している内部圧力を測定するもの。